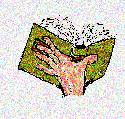
『カラスはどれほど賢いか(都市鳥の適応戦略)』著者:唐沢孝一。出版社:中公新書。昭和63年発行
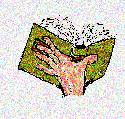
この本を読もうと思う衝動は、前々から興味があったと同時に家族の蔵書棚にあった事もある。
現代人の大多数が都市化には賛成の意を唱えるが、私の場合は反対である。
理由は、都市化=経済都市化であって利益誘導型の画策に過ぎないからである。
なのに、またなぜ日本は車社会を謳歌するのか?意味が解らない。
交通網が便利になればなるほど、個人で楽しむ?車の意味を失くすのではあるまいか?
広大な場所での運転はとても気持ちいい。アメリカやドイツなどの高速道路。とばして
走りたい。
日本は後付けの道路網だから、料金所や出口が判りづらい。特に首都高なんて・・・。
無論、どんな交通手段を利用しようが“カラスの勝って”でしょうが・・・。
1.カラスの生活と都市のゴミは、採餌において非常に密接になっている。
銀座に出没するカラスは、新宿御苑・明治神宮・自然教育園などを塒(ねぐら)にし、採餌の時刻になると
渋谷・新宿・銀座などの残飯をあさりに来る。でも、実際は、最初にホームレスさんなどがあさり(野良
猫等も)、その後をカラスが荒らす。だから、人間が散らかすから網とかでは防げないんだねこれが・・・。
2.人を襲うカラス。
これは、彼らの防御本能からくるもので「巣に近づかない」「幼鳥などを捕まえない・からかわない」など
の注意をすれば繁殖期以外は人を襲ったりしないそうだ。向かってけば、逃げるもんね。
3.環境に関するトラブル。
巣を作る場所として、電柱に作ったり、多人数の観客などが集まるスタジアムの照明器具の所とかに作ら
れて電気系トラブルを起こしたりするとある。これは、如何にもならないよね。人が入る(修理・メンテナンス
の意味合いから)から、人が作業できないとね・・・。人が入れればカラスも入れる。
カラスが入れなければ・・・人も危険で入れない(原発?笑)。
巻末には、カラスは昔の習わしで善く理解されても居ると書かれてる。
頭がいい鳥であるがゆえに無視できないんだね。
私にあだ名を付けた先生(公立学校のね)は、何処までカラスを理解してるかわからないけど・・・
(見た目が似てるからなんだけど)、賢い所もそっくり?だと思う(笑・冗談)。